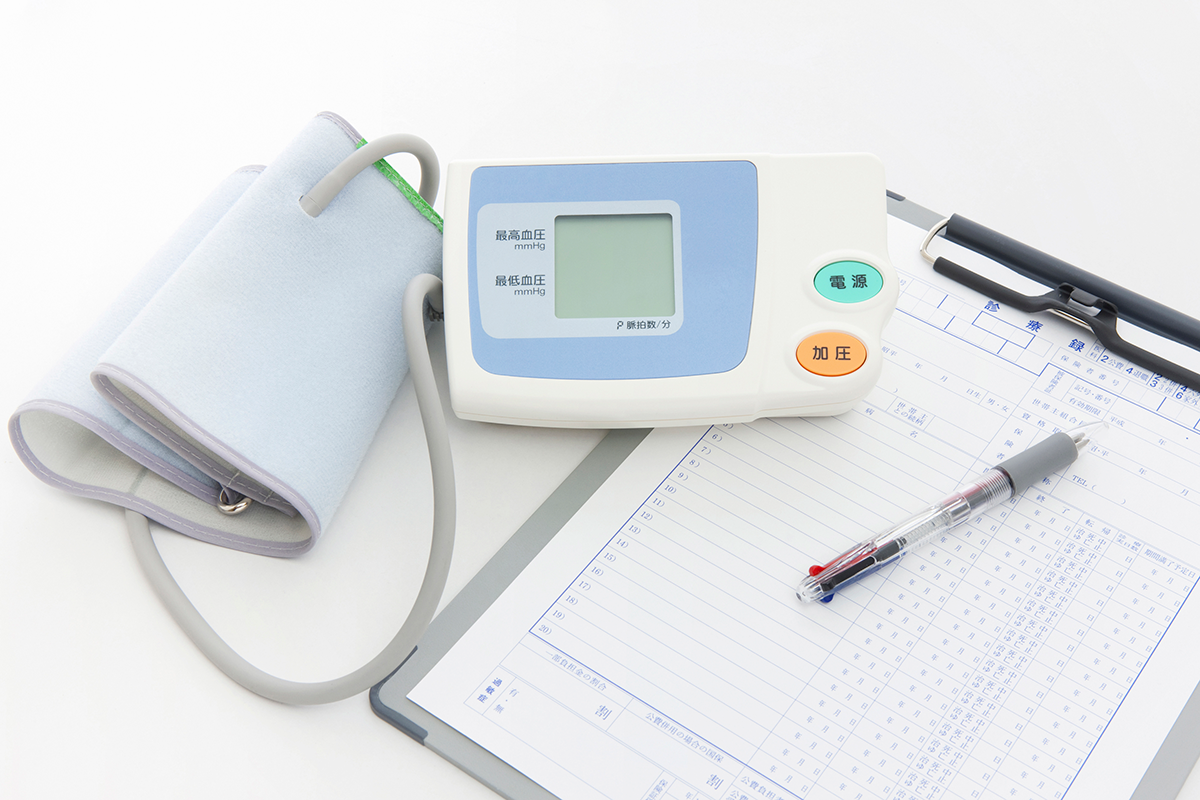クリニックによる糖尿病センターを目指しています。
医療脱毛・美容医療・AGAの治療にも対応します。
クリニックによる糖尿病センターを目指しています。
医療脱毛・美容医療・AGAの治療にも対応します。
お知らせ
ごあいさつ
糖尿病診療を中心に、循環器疾患・AGAの治療・医療脱毛・美容医療など幅広く対応します。
当院は2004年に、院長の大学病院・総合病院での糖尿病診療での経験を地域医療に還元していくため、糖尿病を専門とした生活習慣病の専門クリニックとして開院しました。
糖尿病の治療経験をもとに、近隣の眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科とも連携し、クリニックレベルでの糖尿病センターを目指して診療しております。
当院では外来での診療のほか、独自で考案した食事療法「食べる順番療法」や、運動療法「スロースクワット」を推進しており、患者さまの日々の取り組みにより、食後の血糖上昇を抑制できるように指導も行っています。
糖尿病性合併症だけでなく、狭心症・脳梗塞などの動脈硬化症の診断や、AGA治療にも取り組んでいます。
2023年11月より医療脱毛・美容医療を開始いたしました。
医院案内


医院名梶山内科クリニック
住所〒600-8898
京都市下京区西七条東御前田町20番地1
京都五条クリニックビル2階
TEL075-326-8739
FAX075-326-8741
休診木曜・土曜午後・祝日
| 診療時間(保険診療) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ● |
| 16:00~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
●:日曜は第1日曜のみ午前10時から診療いたします。(原則予約の方のみ)
循環器内科の診療は、火曜日の午前です。
診療の受付時間は午前診は12:45まで、午後診は18:45まで。
初診の方は事前に電話で予約をお願いいたします。
| 診療時間(美容診療) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
交通案内
| 住所 | 〒600-8898 京都市下京区西七条東御前田町20番地1 京都五条クリニックビル2階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR嵯峨野線「丹波口駅」より徒歩10分 阪急京都線「西院駅」より徒歩15分 |
| 最寄りバス停 | 京都市営バス・京阪京都交通・京都バス「市立病院前」バス停から徒歩1分 |
| 駐車場・駐輪場 | 駐車場(ビル南側隣接駐車場に契約駐車場26台) 駐輪場(30台) |